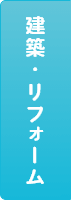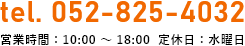カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/07/15 10:00
相続税の仕組みと計算とは?
こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。
リニューアルオープンから
もう1か月が経ちました。
時間が過ぎるのが早いです。
その際にいただいたお花や
観葉植物は元気に育っております。
会社の中を明るくしてくれる存在です。
さて、今回は相続税のしくみと計算について
お伝えしていきます。
- ○土地や建物を相続したときには、相続税がかかる場合がある
- ○相続人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び一定の親族
- ○相続人ごとの法定相続分を用いて、相続税は4つのステップで計算
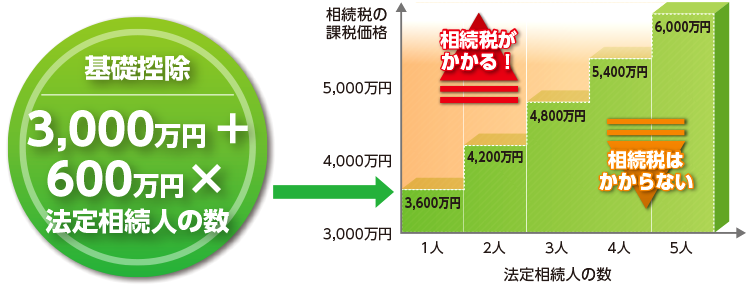
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する
一切の権利義務を相続人等が受け継ぐことをいい、
この相続によって取得した財産にかかるのが相続税(注1)です。
相続人とは、
被相続人の配偶者及び一定の血族関係にある人をいい、
配偶者以外の人が相続人となるかどうかは、
次のように一定の順序が定められています。
この相続順位に応じた法定相続人ごとに、
相続により取得する財産の割合の目安として
法定相続分(注2)が定められています。
- (注1)相続税は、遺言による贈与(遺贈)に
- よって財産を取得した場合や、贈与者の死亡によって
- 効力を生ずる贈与(死因贈与)によって
- 財産を取得した場合にも課税されます。
- (注2)被相続人は、遺言によって
- 法定相続分と異なる相続分を定め、
- また、相続人以外の第三者に
- 遺産を分与することもできますが、
- この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人は、
- 遺留分(法律上、取得することが
- 保障されてる権利)を有しており、
- これは被相続人の財産の2分の1
- (相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)の
- 割合とされています。
遺留分を法定相続分により分け合います。
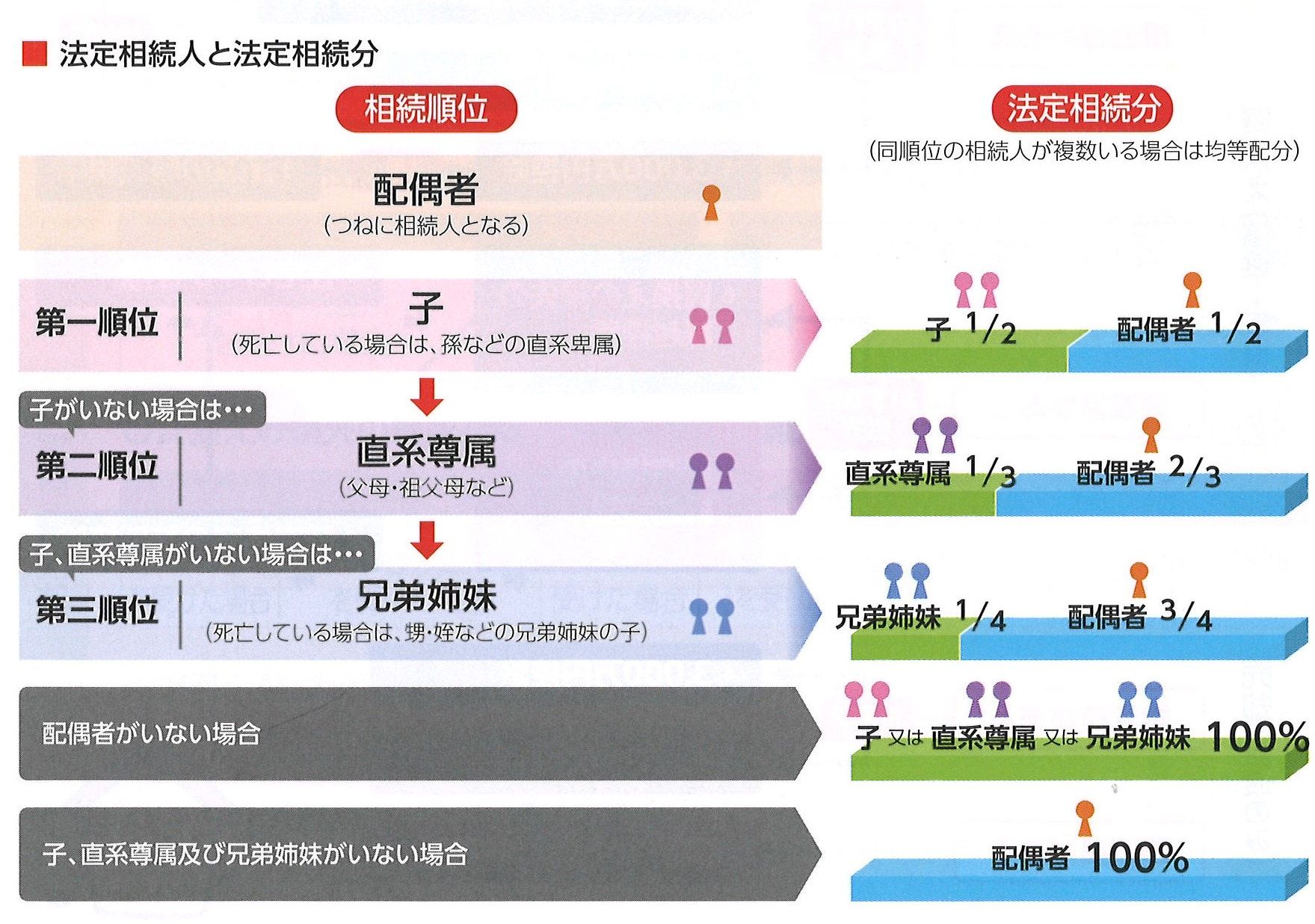
相続税がかかる財産とは?
相続税がかかる財産とは、
相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされ、
土地建物や現金、預貯金、有価証券などはもちろんですが、
死亡保険金(注1)や死亡退職金なども、
「みなし相続財産」として課税の対象となります。
ただし、非課税財産として、
死亡保険金及び死亡退職金については、
それぞれ「500万円×法定相続人の数」による
金額まで非課税となる規定があります。
また、墓所、霊廟、仏壇、仏像などの財産(注2)や
認定NPO法人に寄附をした財産なども
相続税が非課税とされています
(土地建物の評価方法は土地建物の評価額、土地建物の財産評価参照)。
- (注1)被相続人の死亡を保険事故として取得したもので、
- 被相続人が保険料を支払っていたものに限ります。
- (注2)商品、骨とう品、投資対象であるものは除きます。
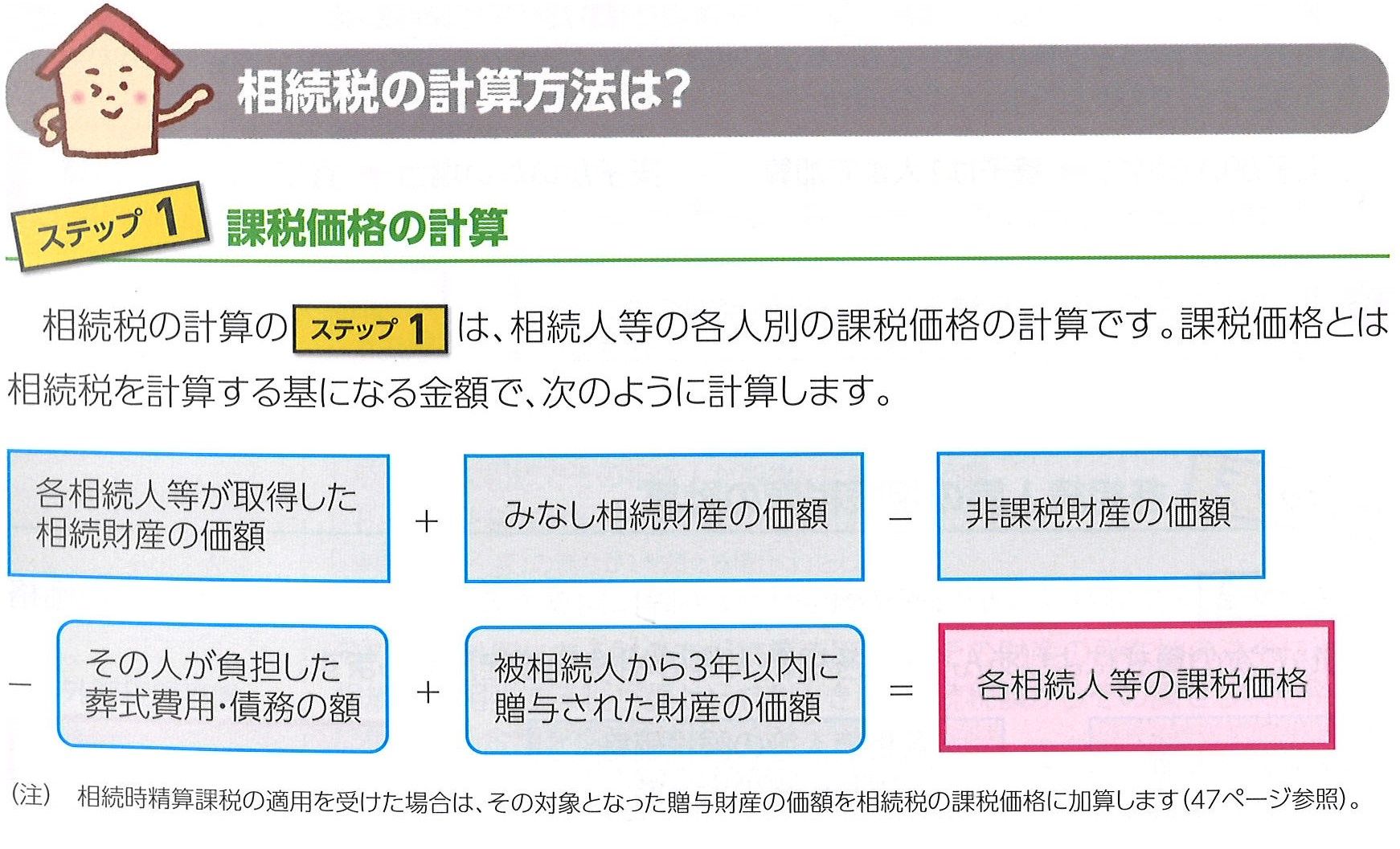
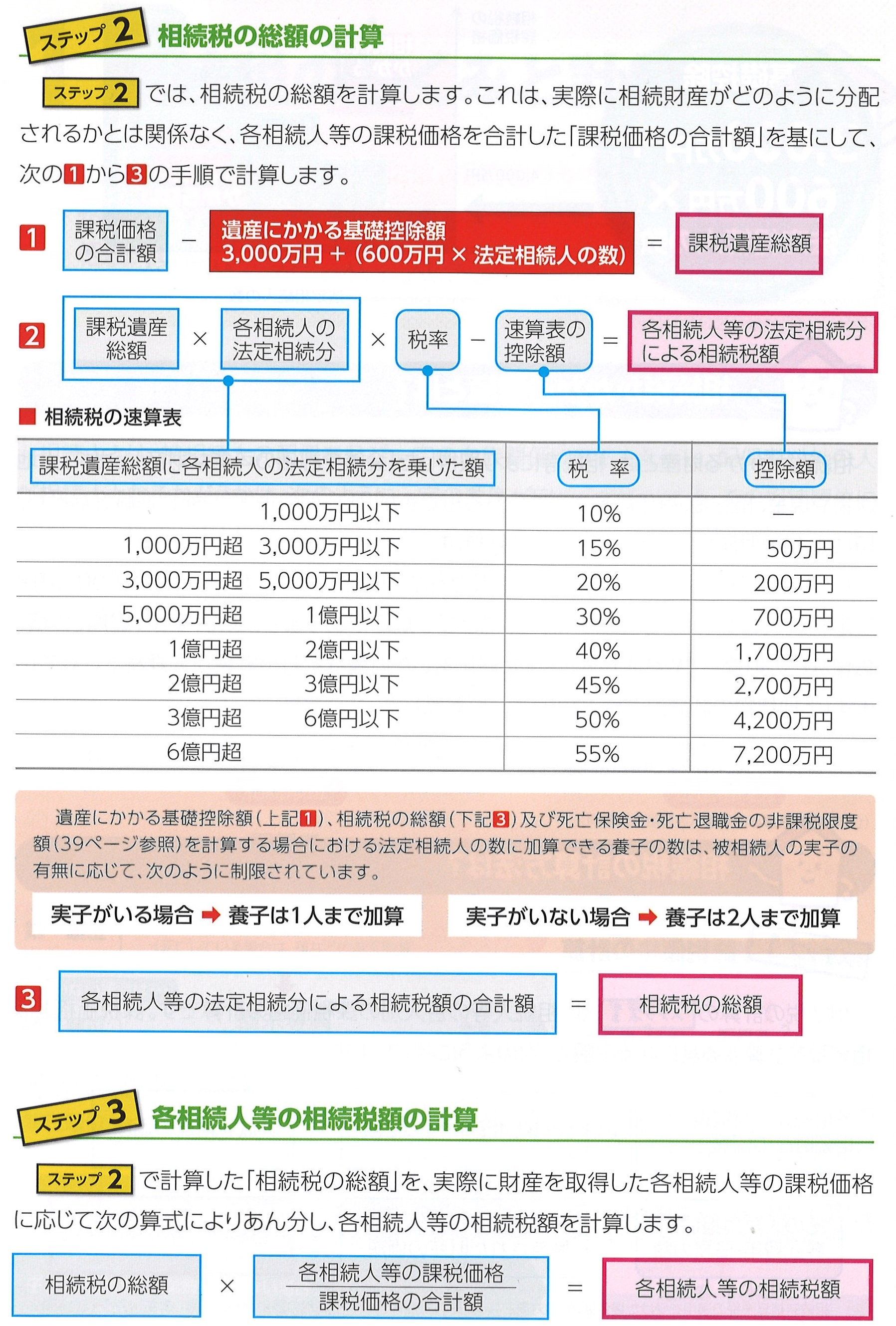
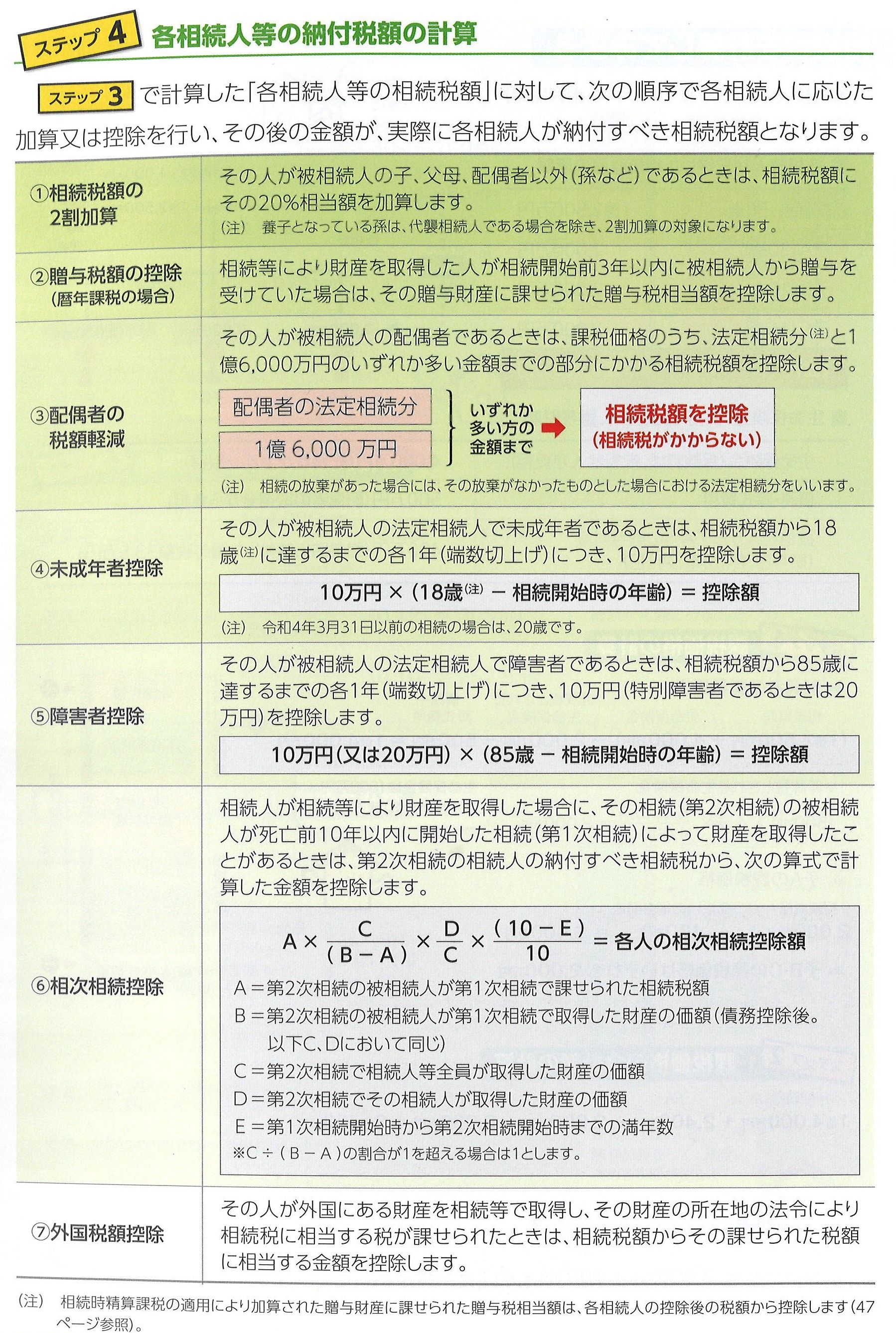
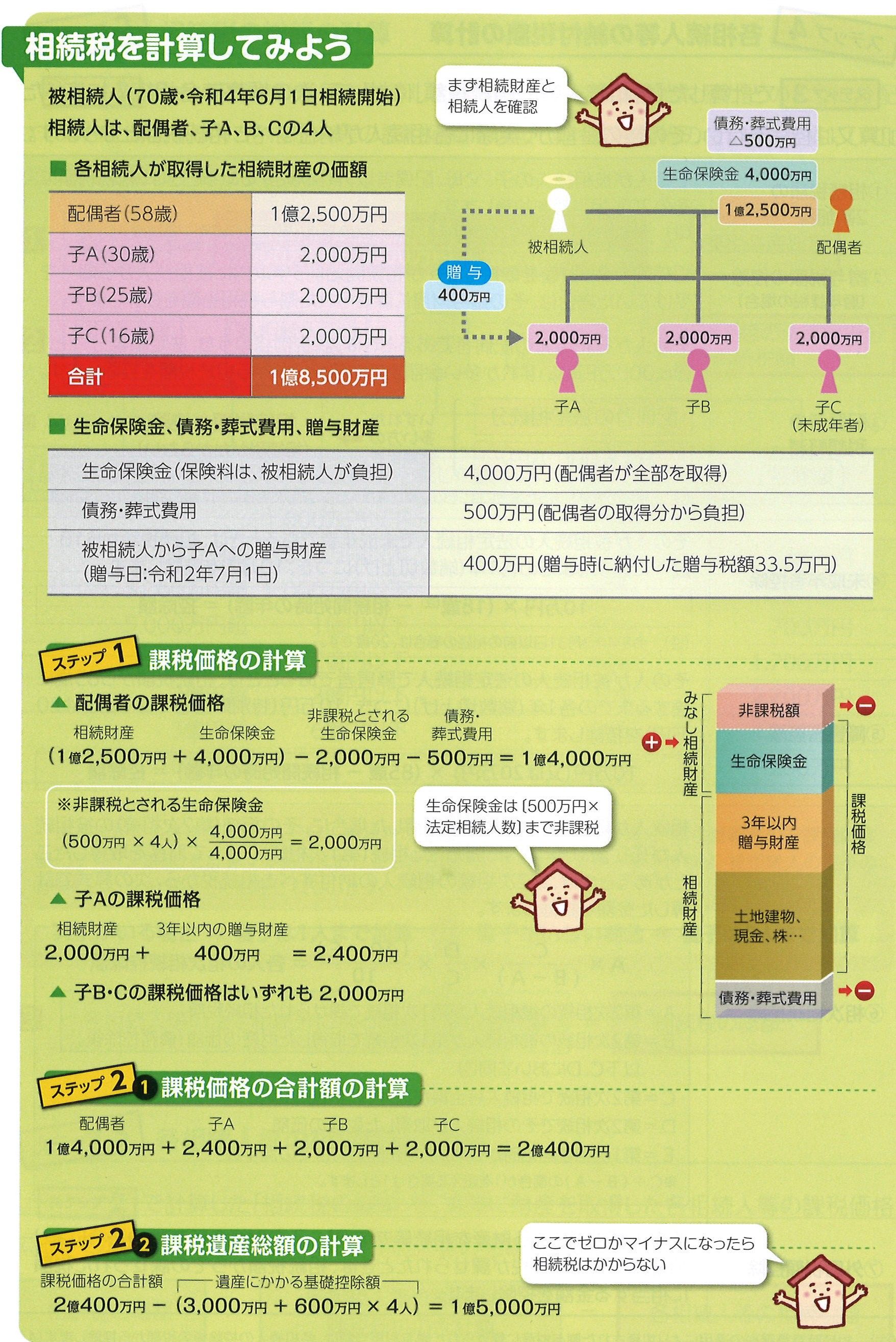
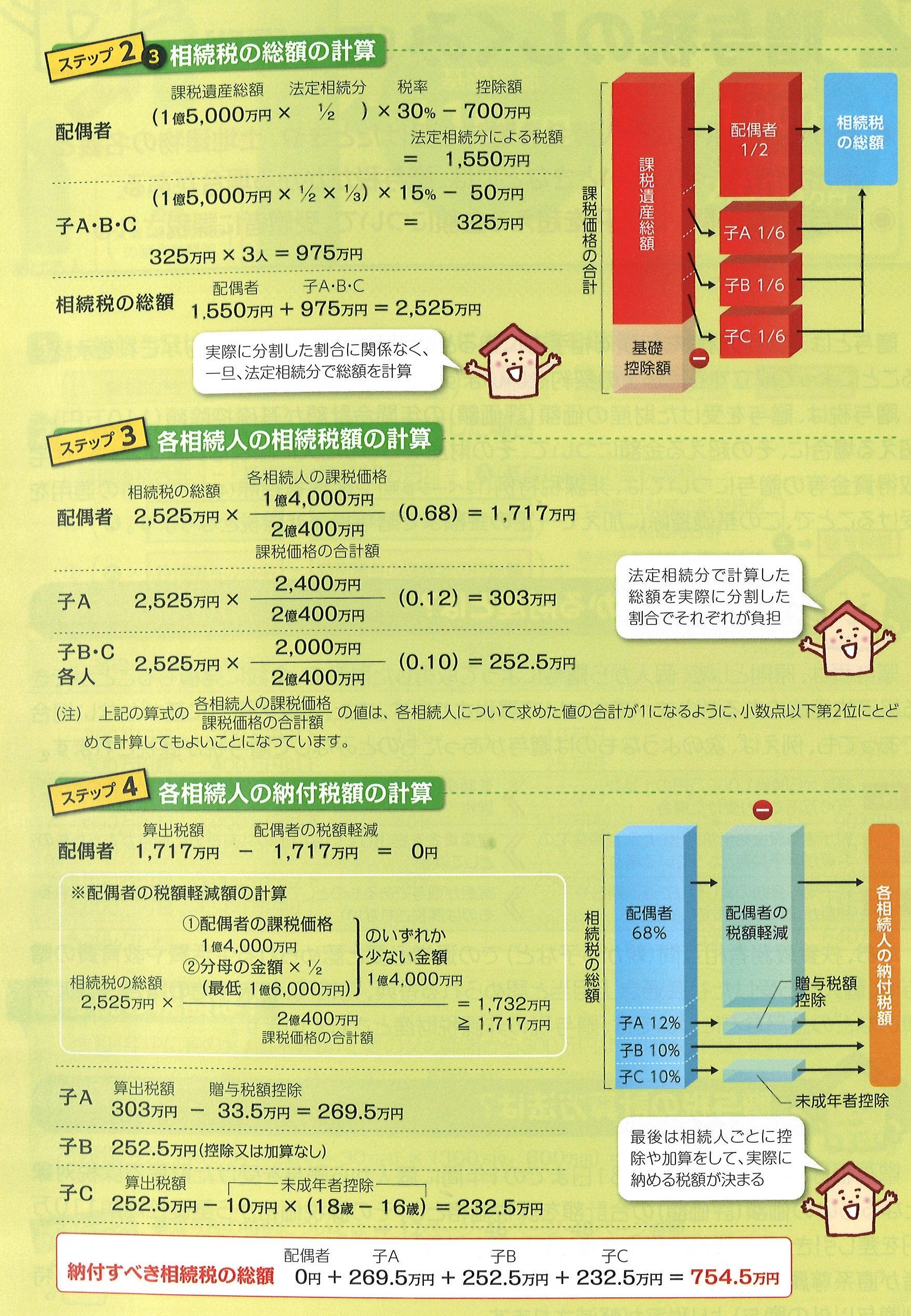
相続が起きるときは
精神的につらい状態だと思います。
そのときにこの仕組みを
わかっている方が色々と
スムーズに進みます。
どうしたらいいか、
あらかじめわかっていると
いざという時も安心です。
ご自身でよくわからないときには
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
▼▼▼

最後までお読みくださり
ありがとうございました。